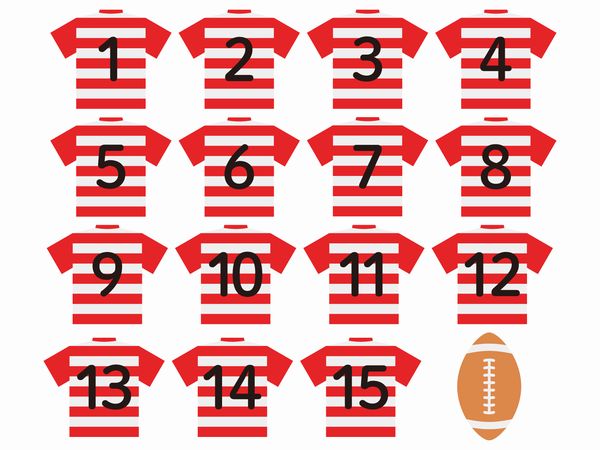日本を背負って戦うものが日本代表
日本代表の選手の中に外国人がいる。
これがラグビーの魅力でもあるんです。

ほかのスポーツでも外国出身の人が日本国籍を取得して日本代表になるということはありますが、ラグビーは日本国籍を持っていない外国人も日本代表になれます。
ラグビーの場合の国(地域)の代表になれる条件は下記のいずれか。
- (ア)その国(地域)で本人が生まれた
- (イ)両親、祖父母のうちのひとりがその国(地域)で生まれた
- (ウ)本人が60か月以上継続して、その国(地域)に居住している
- (エ)本人が通算で10年以上、その国(地域)に滞在している
これが国際的なルールで日本代表だけのルールではありません。
他の国の代表にも、その国の国籍以外の選手がいます。
日本人の中に外国人がいると目立ちますが、外国人の中に外国人がいても日本人にとっては気づきにくいんですよね。気づきにくいだけで、ほとんどの国の代表に「外国人」はいます。
所属協会主義というのがラグビーの伝統であり魅力
なぜ、こんな代表資格になっているのかというと歴史的な背景からです。
(いくつか説があるのですが、あまり他で見かけないものを紹介します。)
ラグビーは、もともとイギリスから世界各地に広まりました。オーストラリアやニュージーランドに引っ越したイギリス人が現地で広めたんですね。
となると、最初は現地に渡ったイギリス人がその国(地域)のラグビーの中心選手になります。現地のプレイヤーは、まだ教えてもらってる段階ですからね。
そこで、国同士で試合をしようとなったときに困ります。国籍で国の代表を決めてしまうと、その国(地域)の中心プレイヤー(イギリス人)が代表に入れないのです。
この国でラグビーを教えてくれてるのに、この国(地域)の代表にされないなんて、なんだかさみしい。我が国(地域)の代表として、彼に戦ってもらいたい!
そんな気持ちから、その国(地域)でプレーしている人の代表同士で戦おうということになりました。所属協会主義ってヤツです。
これが現代の代表規定にも残っているのです(あくまで一説)。
イングランド代表、スコットランド代表とは
このページで、『国(地域)』と国だけではなく地域も入れていたのには理由があります。
ラグビーのW杯にはイギリス代表ではなく、イングランド代表、スコットランド代表、ウェールズ代表、アイルランド代表が出場します(サッカーと同じ)。国ではなく地域ですよね。
これも不思議ですよね。
理由には、いくつか説があります。
個人的に気にっている説はイギリスという国が誕生するよりも前に、イングランドラグビー協会、スコットランドラグビー協会があり、それぞれの代表が試合を行っていたからというもの。
国よりも地域(イングランド、スコットランド…)の愛着が強いんですね。
ちなみに、W杯には参加していませんがアジアにも香港代表があります。ややこしいので、これ以降は『国代表』に記載を変更しますが、国(地域)と思って読んでください。
その国のために戦うのが代表
国代表の資格には最初に挙げた4つ以外にもうひとつあります。
- ある国で代表になったことがあるものは、その国以外の代表にはなれない
つまり、日本代表になった外国人選手は、母国(自分の出生国)の代表にはなれないということです。これもどの国の代表でも同じ。
このため、ある国の代表に選ばれても(打診があっても)辞退するという選手もいます。
ということは、日本代表になってくれた選手は母国の代表を捨て、日本のために戦ってくれてるということです。南アフリカ戦後に五郎丸選手が言っていたのは、このことです。
いまや、母国の代表になれなかったような選手が日本代表になっている時代ではありません。そんな選手は日本代表にもなれません。
グローバル時代のスポーツ
国籍など関係なく外国人も一緒になって日本のために戦う。
これこそがラグビーの魅力です。
グローバル時代のスポーツらしくて私は好きです。